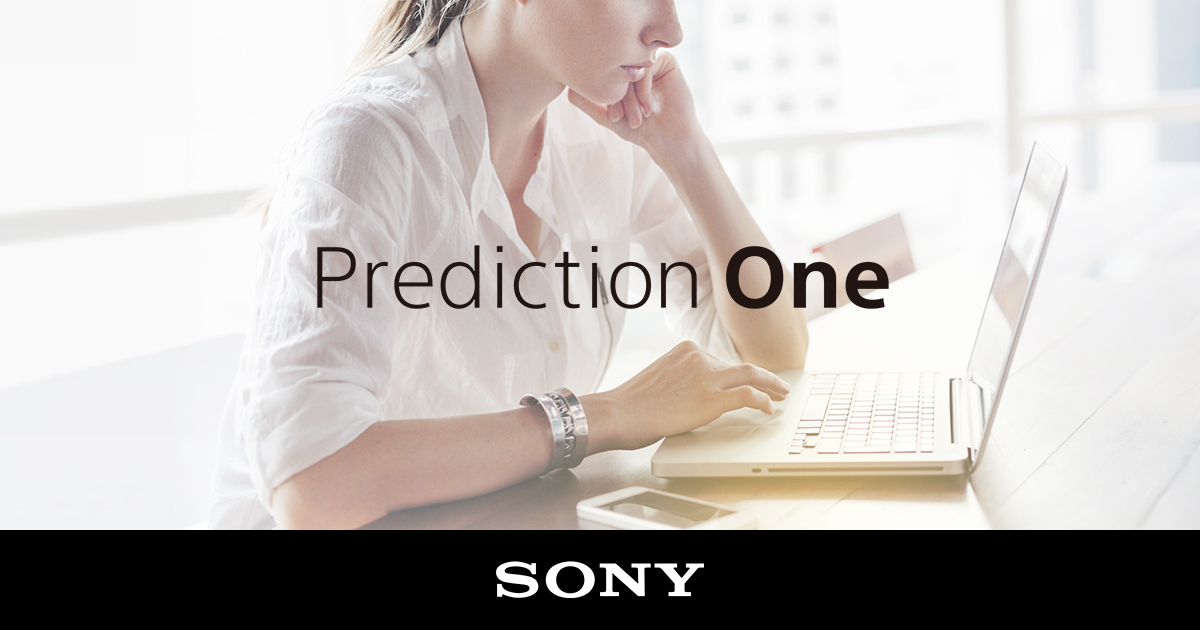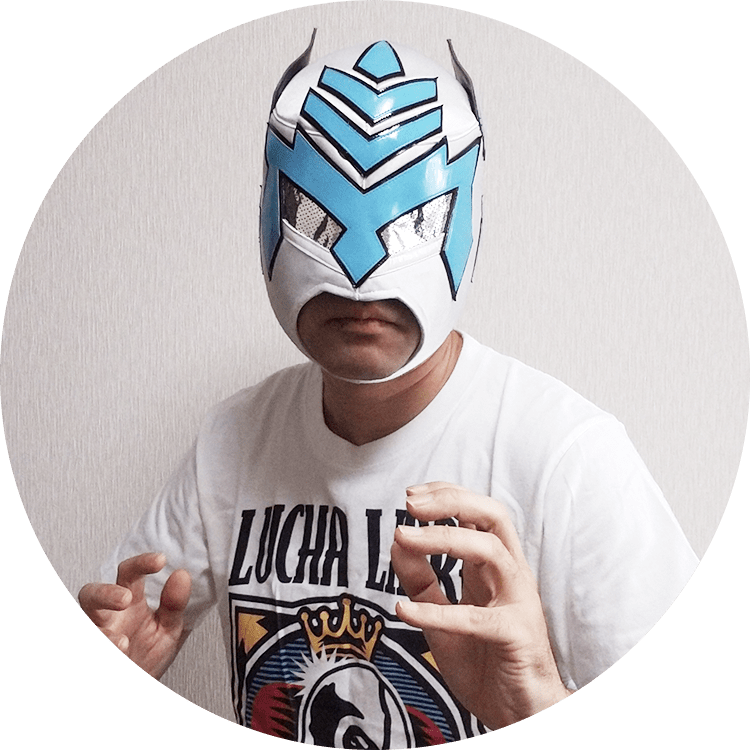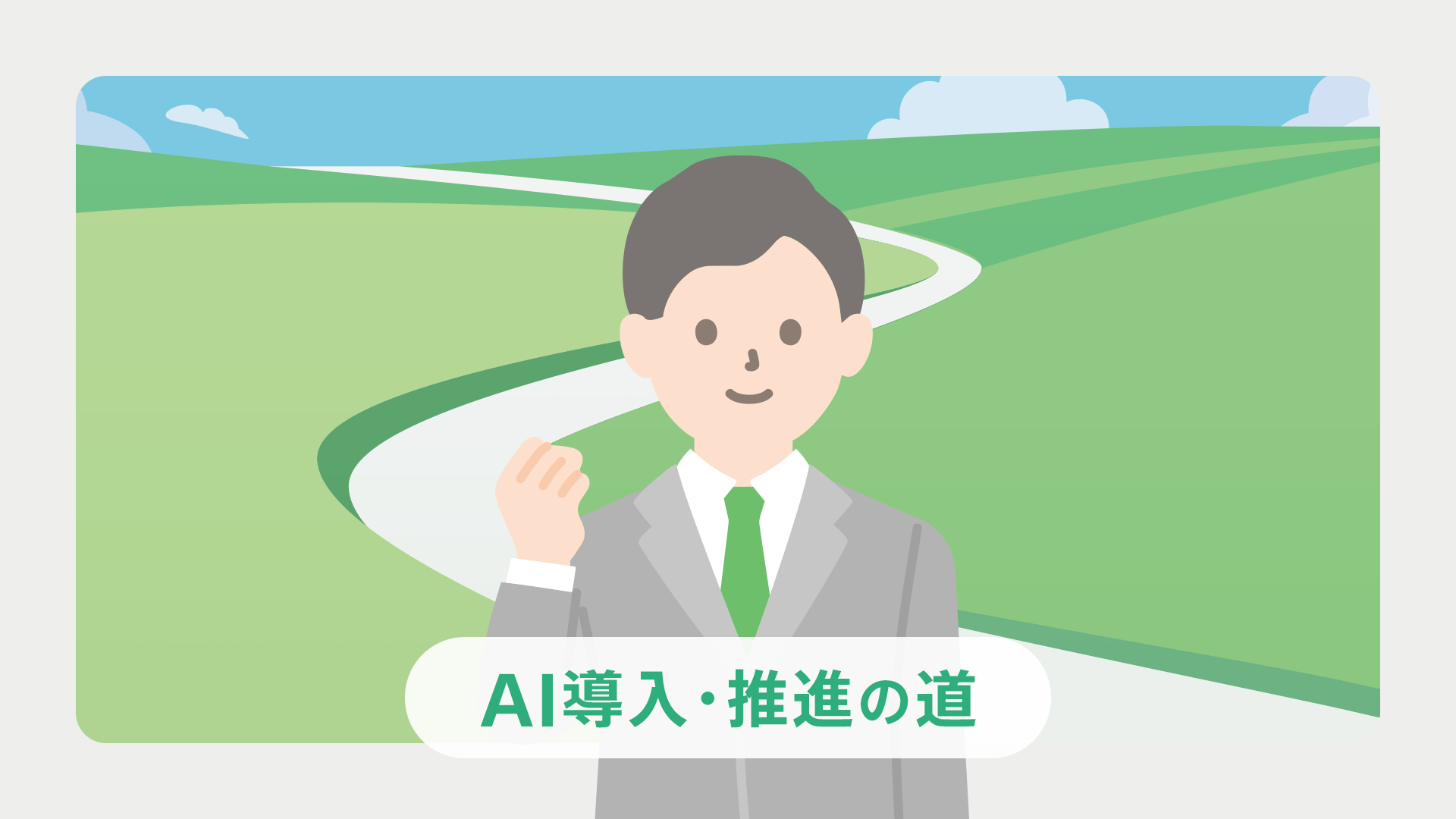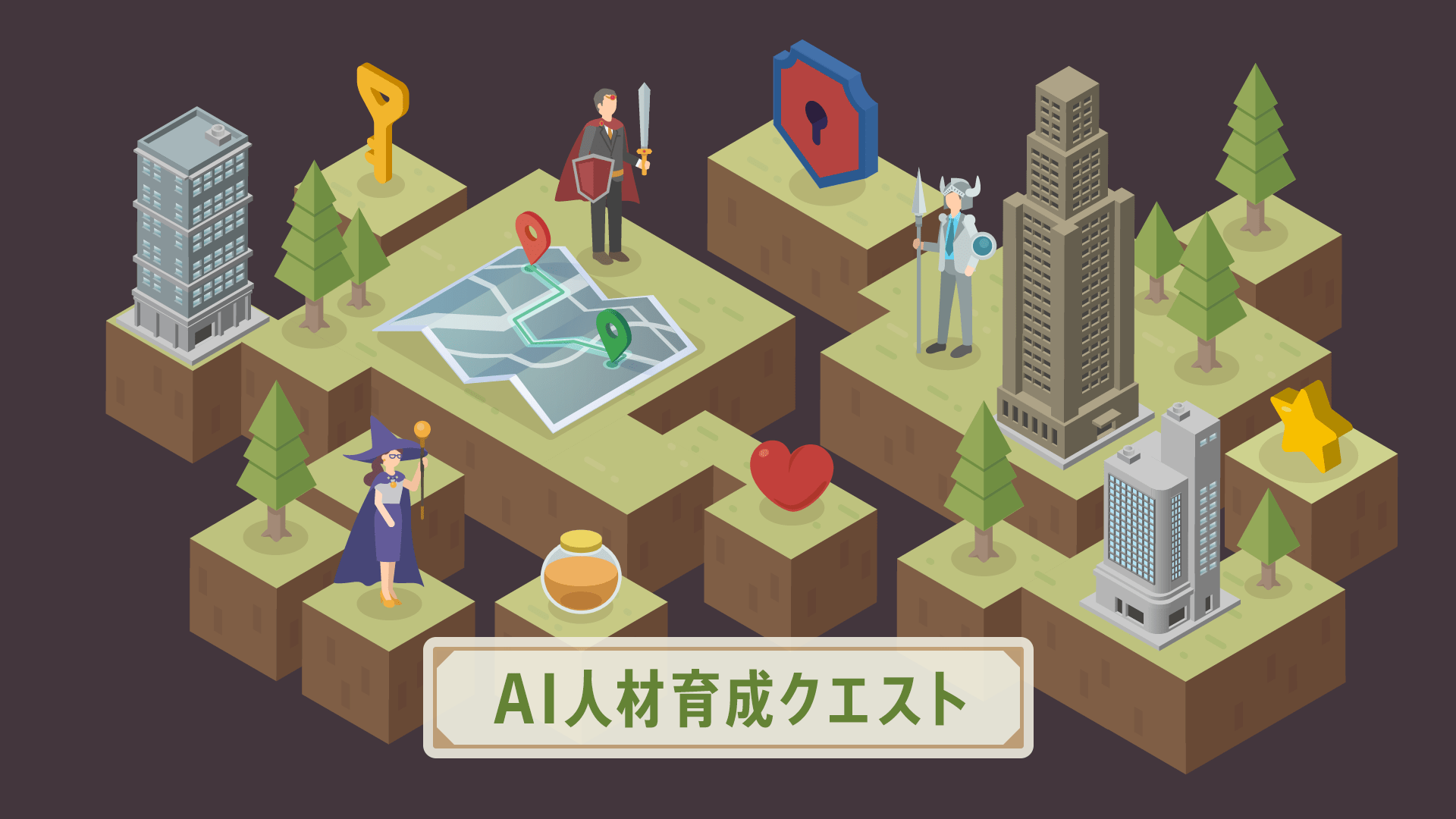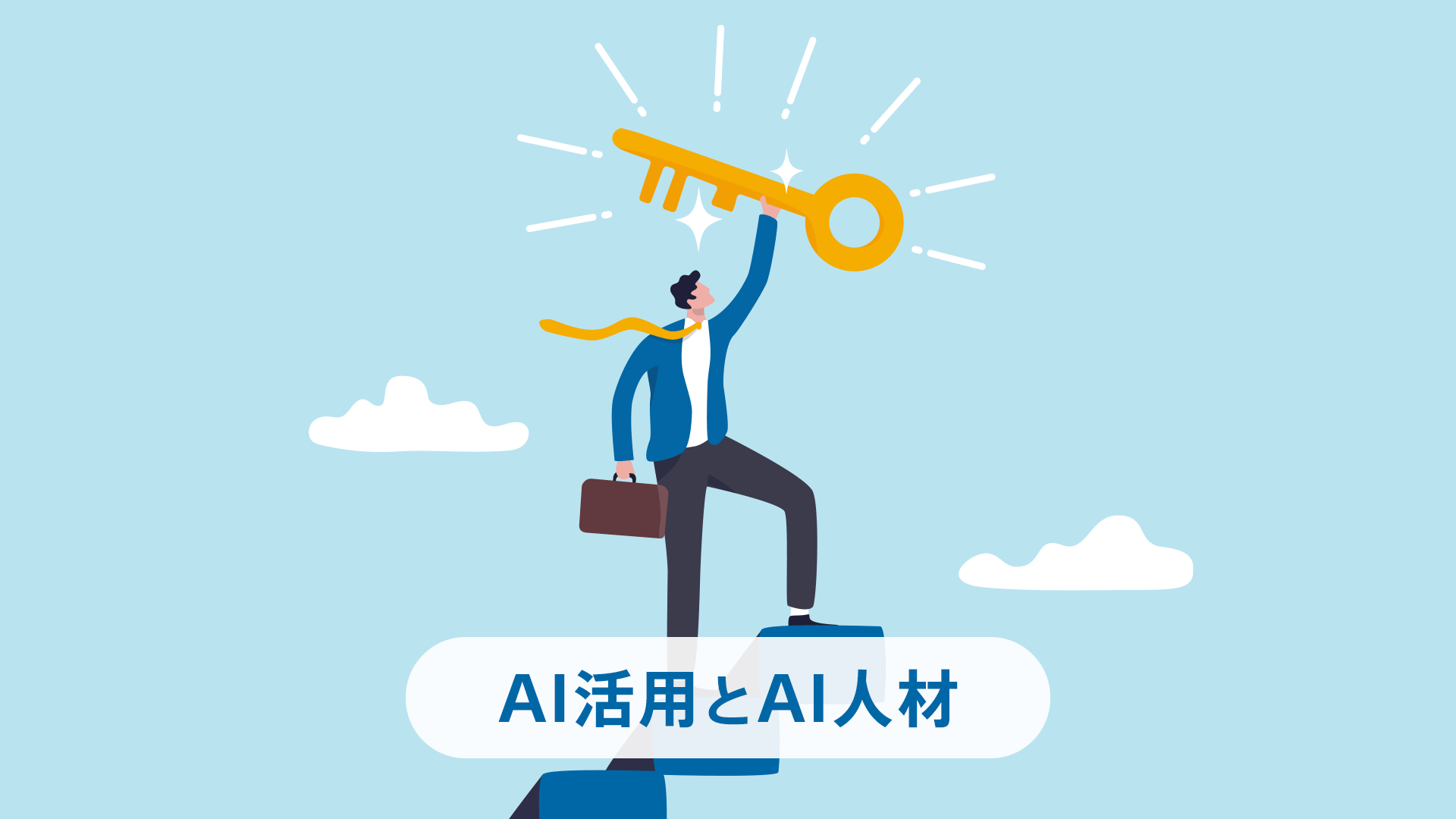推進ノウハウ
AIによって人間の仕事がなくなる?
~AIを知り業務を知れば百年殆からず~
#AI導入
#AI活用
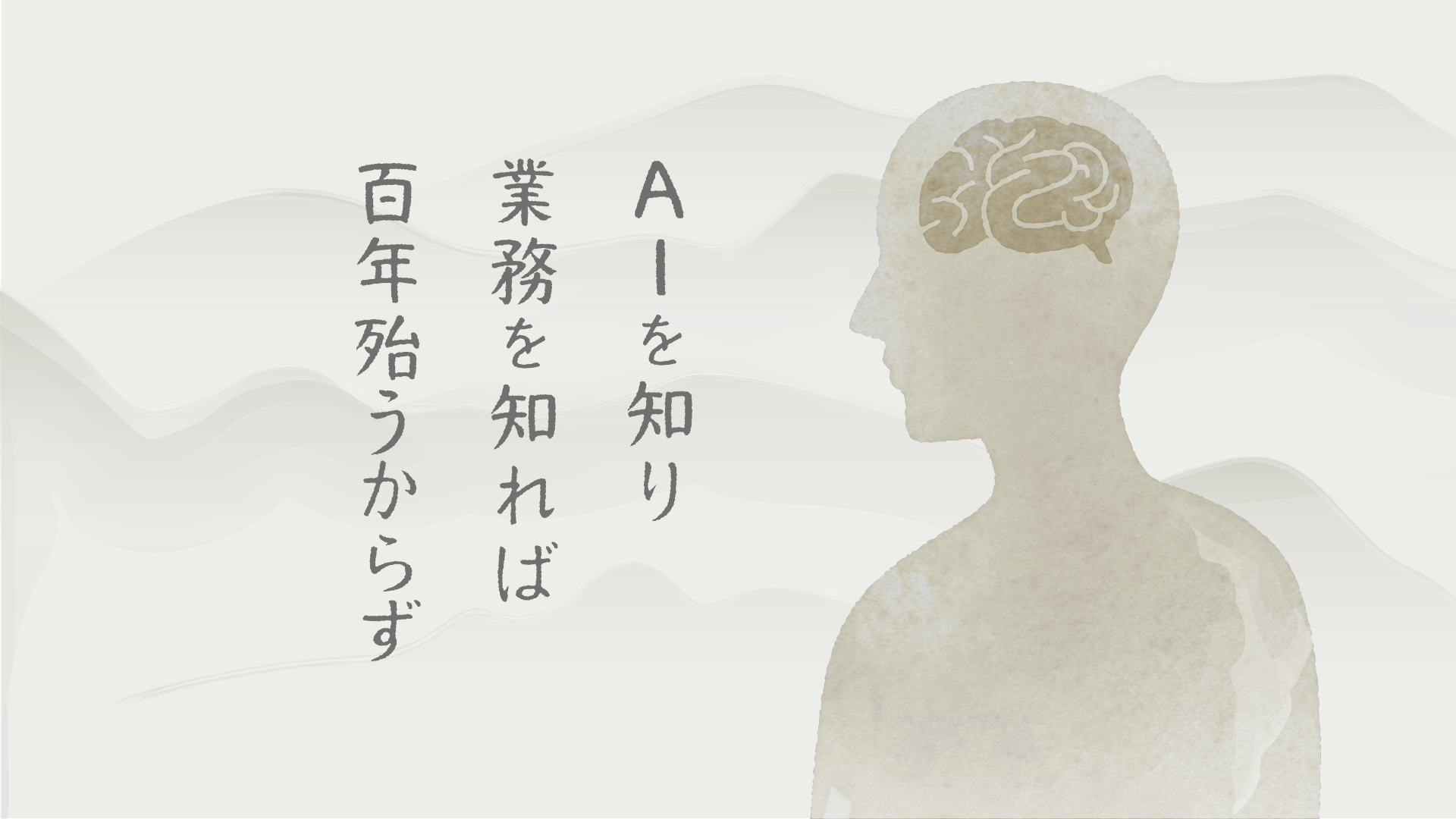
AIについて基本的なことから学びたい方は、こちらの資料がおすすめです。
「AIリストラ」は現実になるのか?
AI導入において最初に挙がる不安は、「AIに人間の仕事を奪われるのでは?」という懸念でしょう。
AIの性能が向上する中で、対応できる仕事の種類も増えていきます。そして、人間がやっている仕事をAIにやらせるなら、人間はいらなくなります。しかも、AIは24時間働き続けても文句を言いませんし、賞与も残業代も労働基準法も関係ありません。
労働者としてAIと人間を比較
| AI | 人間 | |
|---|---|---|
| 給料 | 最初だけ必要 | 毎月必要 |
| 賞与 | 不要 | 必要(年2回) |
| 残業代 | 不要 | 必要(25%増) |
| 労働時間 | 24時間 | 8時間 |
| 不平不満 | 言わない | 言う |
利益を追求する経営者にとって、安い費用で24時間働くAIは理想の労働者ですが、最終的に人間は不要になるのでしょうか。
省人化の事実としては、AI以前でも仕事においては機械化や自動化は進んでおり、ロボットなどは数十年前から当たり前に使われています。しかし、実際にAIが起こす変化はさらに劇的で影響が大きく、数十年どころか数年で大きな進化を遂げたことは皆様も実感しているでしょう。このままでは人手不足や業績を理由にして、AIに仕事を奪われる「AIリストラ」が現実になるのでは、と不安に思う担当者も出てきます。
過去の歴史を遡っていくと、技術の進歩と人間の仕事における戦いが存在しています。18世紀半ばのイギリスで始まった産業革命では、機械を破壊する労働者が出現しました。それでも50年・100年単位で社会の流れは変わりました。
技術進化やイノベーションは確実に起こり、社会は変化しています。例えば、100年前のアメリカでは自動車王のフォード氏が顧客に欲しい物を聞いたら「もっと早い馬が欲しい」と答えたそうです。それでは自動車は普及しなかったでしょう。馬しか知らない当時の人は、自動車の登場に驚いたはずです。しかし、現代人にとっては生まれた時から自動車があるのは当たり前です。
そして、スマートフォンの登場から約15年が経過して、同様に社会を激変させました。高齢者など、使いこなせない人もいる一方で、10代にとってはスマホを利用するのが当たり前の感覚です。
社会が変化するスピードが年々早まる中で、変化についていけずに新しいものに不安や反発を抱く人も増えています。しかし、AIというわからないものに対して、否定するだけでは解決策にはなりません。
ここで視点を変えてみましょう。
AIを知り己を知る

※AIによる画像生成
そこで「AIを知り己を知る」という考え方が必要です。まずは相手を知ることが重要と言えます。
これは「彼を知り己を知れば百戦殆(あや)うからず」に通じます。意味は「戦争において敵と味方の両方で情勢を把握しておけば、幾度戦っても負けることはない」という意味です。
この考え方は「孫子の兵法」で紹介された一節です。孫子の兵法は戦争における兵の用い方で、書かれた年代は紀元前500年ごろ(現在から約2500年前)まで遡ります。その内容は現代においても古今東西で高く評価されており、ビジネスにも応用されるほどです。
孫子の兵法で語られるとおり、何かと戦うならば相手を知ることが必要です。そこで、AIという敵を知ることが重要となります。AIで何ができるのか、逆にAIは何ができないのか、現在から将来に渡ってAIがどのように進化するかなど、「敵を知る」ことで見えてくるものがあります。AIがどんな用途で使われているのかがわかれば、自分の仕事や会社にどれだけ影響を与えるのかを把握できます。逆にAIが使われていない用途でも、どんな技術進化によってAIが活用可能か予測できるでしょう。
敵を知る次は、己を知ることが重要です。孫子の兵法における戦争でも、相手を調べるばかりで自分を調べず、自分を過大評価するのは避けねばなりません。会社や仕事に当てはめると「自分の仕事ができるのは自分だけ」「自分の仕事はAIにはできない」という思い込みと言えます。自分の仕事は本当にAIのみならず他の人間でもできないことでしょうか。そもそも特定の人物に業務や知見を依存する属人化は、組織として不利益も大きく、組織としては避けたいものです。そこで自分の仕事をこなすには、どんな経験やスキルが必要なのかを改めて把握しましょう。いずれ他の人やAIが引き継ぐので、必要なことです。こうして「己を知る」きっかけとなります。
ここで考えられる人間が果たすべき役割は、自分の知見を代替となるAI(あるいは他人)に学習させることです。
AIであっても最初は知識がないので、データを用いて学習しなければいけません。この学習に用いるデータの品質が悪いと、AIの性能が低くなり使い物になりません。そもそもAIが対応できる作業は、決められたルールに沿った作業であり、個別に専門知識が必要な作業には不向きです。例えば、特定業務に起因する知識や企業内での作業手順といった仕事の進め方など、ネット上で公開されていなかったり、明文化されていない業務はAIが苦手な分野です。しかし、こうした分野もいずれAIの支援が必要になります。こうした業務を理解して、学習可能なデータを用意できるのが人間の価値であり、AIにとって難しい事です。このような分野はAIでは替えが効きにくいので、差別化しやすい業務と言えるでしょう。
また、孫子の兵法では「五事」「七計」と呼ばれる実情の比較や分析に注目しています。特に、兵を率いる将軍が重要です。将軍は学習データの対象となる人間の立場であり、AIは命令を実行する兵士です。優秀な兵士を活躍させるため、AIを訓練して鍛え上げることが会社全体でのメリットにつながります。
こうしてAIという後進を育成するつもりで、自分の業務に向き合ってはいかがでしょうか。
企業へAIを導入する際に準備すべきことを解説した記事はこちらから
そもそもAIと戦うべきなのか?
そもそもAIと人間は戦うものでしょうか。AIと戦って勝ったところで、いずれAIは進化して人間を越えていきます。これはチェスや囲碁などで既に起こっています。そして、孫子の兵法では「百戦百勝は善の善なるものに非ず。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」とあります。これは「最善の策は下手に戦わず敵を従わせること」という意味です。
ここで考えを改めてみましょう。そもそもAIはあなたの仕事を奪う敵ではなく、同じ仕事をする協力者とも考えられます。それなら、AIを自分に取り込みつつ、パートナーとして使いこなす方がずっと有効です。
具体例として、このような使い方があるでしょう。
- 画像から間違いや違和感などを検出させる
AIが補助するなら? → 製造現場で、人間の目や耳で検知する異常判断の支援 - 大量の文章から方向性を読み取らせる
AIが補助するなら? → マーケティング領域で、人間が処理するには膨大すぎるSNSの口コミ情報の分析 - 画像や文章の元になる案を生成させる
AIが補助するなら? → クリエイティブで、アイデア出しやイメージ案の作成など大量の素案・素材の準備 - 他人の意図や表情などを読み取らせる
AIが補助するなら? → 受付関連で個々人によって分かれてしまう判断をAIによって統一
個々の人間においては、上記には苦手な作業があるでしょう。そこをAIが対応すれば、自動で欠点を補ってフォローしてくれます。
しかし、AIと言えども完璧ではありません。AIの強みと弱みがわかれば、AIが人間に勝てない部分で競ったり、人間の弱点を補うように手配すれば良いのです。こうした考え方に切り替えながらAIと自分を深く知ることで、孫氏の兵法にある「戦わずして兵を屈する」という最善策につながっていくでしょう。
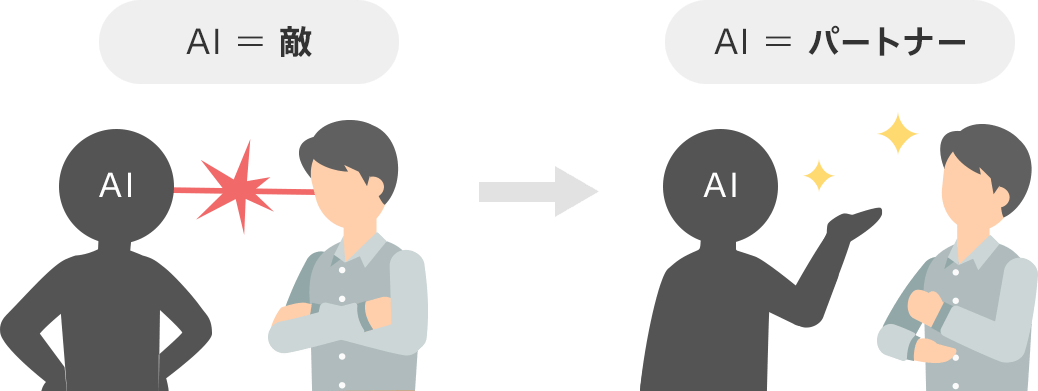
まとめ:AIを知り業務を知れば百年殆からず
今後、AIが急速に進化するのは事実ですが、それでも限界はあります。そして、人間にもできることと、できないことはあります。どちらも異なる存在であり、単純に比較や置き換えができる存在ではありません。それでもAI導入に不安を覚えるのは、AIがどんなものかわからないためです。わからないものを怖がり、拒否するのは自然なことですが、現代社会では仕事や生活においてAIとの関わりは避けられません。
いまや人生100年時代と言われます。これから仕事する時間が長くなれば、AI以外にも様々な変化は避けられないでしょう。さらに、日本の労働人口は減少の一途です。
こうした新たな変化や課題に対して、どのように対処すべきでしょうか?2500年前から現代まで語り継がれる孫子の兵法で、乗り越えていきましょう。